私はよく泣く。実在する人物でも、架空の人物でも、その人にいいことか、もしくは悲しいことが起こると、私は泣く。他の人が泣いているのを見たとき、私は泣く。
私はかなり簡単に泣く。そのことは、公の場でだと特に、気恥ずかしい。一番ひどく泣くのは何かが終わろうとしているとき、特に最後の日だ。私はかつて、日本の空港の出入国管理のカウンターで泣き腫らした。これが最後だと思いながら自分の在留カードを手渡したとき、自然発生的に、まるで彼が私の日本での時間を担当していたかのように、出入国管理職員に対してお礼を述べ始めた。むせび泣き混じりに私が言ったことをどれだけ彼が理解したか分からないが、彼は私の在留カードを両手で受け取り、ぎこちない笑顔を何とか作って見せた。
生まれ変わったら、日本の終身雇用のスタイルは私には合っていただろう。なぜなら、それであれば自分が退職する日に泣くのは1度だけだからだ。
実際はそうではなく、私は仕事を何度も変えていて、最後の日はいつも涙ながらだった。ある仕事では、私はみんなが四半期の会議をしている間に建物を去った。お別れと感謝のEメールを送って、泣かずに済むようにその場を去った。
日本で初めて勤めた会社での最後の日には、みんなに感謝を伝えようとしていたときに、突然感情で胸がいっぱいになり、最初の一文を言い終わる前に涙が流れ始めた。私の上司は、私が深く尊敬していた真面目な日本人女性で、私を引き寄せてしっかりと抱きしめてくれた―そのことはありがたかったが、余計にむせび泣きが増した。
イギリスでは、上司と私が人事部の部長に私のビザの延長について話しに行ったときに、それが不可能だという悪い知らせを受けて、私たち二人は人事部長のオフィスで泣いた。彼女はティッシュの箱を私たちに差し出したが、一切泣かなかった―それはたぶん、彼女の仕事において持つべき優れたスキルだ。
しかし、映画『Inside Out(邦題:インサイド・ヘッド)』で見事に示されているように、悲しみなしに喜びはない。このことについての私の最初の記憶は、幼稚園の初日のことだった。ここにいる知らない人たち全員と一緒に私を一人残して母が去ろうとしていることに気が付いたとき、私は泣き出した。しかし、涙のカーテンの向こうに、小さな人影が私の方へ向かってくるのが見えた。母を見る最後になるだろうと私が思った出来事は、人生初の友達との出会いとなった。私たちはとても長い間、切っても切れない関係で、数十年間が経った今でも連絡を取り合っている。
私の経験から考えると、悲しい「最後」が続くことはないようだ。私が泣くのは、たくさんの喜びから去ろうとしているから、もしくは、すぐそばに見つかる何かの喜びがあるから。私はただ、ティッシュをたくさん用意しておく必要があるだけだ。

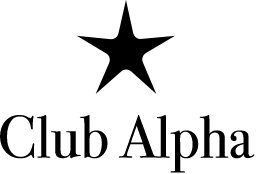



 毎週届く!
毎週届く!

